|
2025/05/15 03:39
|
|
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
|
2007/07/28 02:43
|
|
大人の立場になってわかることがある。 少年は「笑い」に重い価値を置く町に生まれ育った。 週末ともなれば朝から晩まで漫才師や落語家やコメディアンがテレビに出っぱなしの異様な状況に浸かれば、笑いを生みだす者こそが英雄という考えに至るのは自然であり、「おもんない」「しょうもない」などの言葉は、彼にとって全人格を否定される屈辱的な罵倒だった。 彼だけでなく、周囲の仲間の価値観も同様だった。そして、笑いをとるためなら多少の犠牲も厭わない破綻者も数多く存在した。 流行っていたB&Bの模倣に走るアホ連中による 「先生!」 「なに?」 「呼んでみただけ」 のやりとりにいいかげんキレた教師が「今度先生に『呼んでみただけ』と言ったやつは容赦なく廊下に立たせる!」条例を発令したりしたのも、その一端といえるだろう。 大人をいじる限界点を見誤った仲間たちが次々と廊下送りとなった。少年は引き際を察知する能力が非常に高く、二回しか立たされずにすんだ。 そんな彼らにとって「お楽しみ会」は最重要イベントだった。まさに人間そのものが評価される試練の場なのだ。 一週間ほど前から班のリーダー宅で毎日ミーティングを開き、ネタを練り、通し稽古を行い、全身全霊を奉げて臨んでいた。今になって思えば「そのエネルギーを別のことに使え」である。 他にも、作文、図工、家庭科や夏休みの自由研究において学業的なノルマをクリアしつついかに笑いをとるかなど、発表の場は数多くあった。 以前この場で書いた「遠足」も、そんななかの一つだ。 もちろん遠足そのものは楽しい行楽イベントだ。課題となるのは「おやつ」である。 しかし「バナナはおやつに入りますか?」など、先人によって踏み固められてしまった定型句では笑いをとれないことがわかっているため、誰も口にしない。 一度「ちりめんじゃこはおやつに入りますか?」で挑んだ特攻野郎がいたが、教師に「入る」と鼻であしらわれ玉砕していた。 それはともかく、例えば「おやつは200円まで」と決められていれば、その条件の中でいかに笑いを誘うかが問題になるのだ。 女子たちが200円をやりくりし、飴やチョコレートやガムを好みの配分で持ってきている横で、ビッグワンガム、とんがりコーン、ブルボンの妙にお高くとまった菓子、鴬ボール、名も知らぬメーカーのクッキー、マルカワ10円ガムやチロルチョコを20個、粉ジュース20袋などを見せ合って品評するのだ。 上級者にもなると、仁丹、干しぶどう、落花生、わらび餅など、いぶし銀のおやつが出揃うこともある。 前述のちりめんじゃこのやつは、ご丁寧に200円の領収書まで持参し、やけくそ気味で教師に提示していた。サムライを見た。 豆を持ってきたやつがいた。節分用の豆で、鬼のお面つきである。 これはどう考えても時期的に辻褄が合わない。つまりそいつは、節分のシーズンにお面つきの豆を購入しておき、この遠足まで眠らせていたということになる。見事な長期計画だ。 鬼の面を被って記念撮影に収まる級友を横目に、少年は負けたと思った。次は必ず勝ってみせると心に誓った。 そしてリベンジの遠足の日がやってくる。 少年の実家は製菓業を営んでいた。彼はお菓子の家に生まれ育った王子様なのだ。 しかし、自分の家で作っている菓子を持っていくなんて短絡的な着地は許されない。実行すれば間違いなくみんなにバカにされる。それ以前にあまりに身近にありすぎて、家の菓子はもう見るのも嫌だというのが大きい。 ここでは限界ぎりぎりの政治力を利用する。インサイダーのコネを駆使するのだ。 彼の実家の周囲には菓子の町工場がいくつかあり、組合を結成していた。その一つに「炭酸せんべい」の工場があった。 製造業の悲しい現実として、どうしても避けられない規格外品ができてしまうことがある。生地が型全体にうまく行き渡らず、不完全な形に焼き上がったもの。逆に生地が多すぎてはみ出し、いびつな形になったもの。また、冷却乾燥の段階で曲がったり割れたりしたものがそれに当たる。 口に入れるには何の支障もないし、もちろん味も変わらない。ただ、売り物として世に出すには職人たちのプライドが許さない、そんなB級品だ。 その工場では小売はしていないため、それらのイレギュラーが一般人の目に触れることはない。ふやかし溶かして、再び生地に混ぜられるエコな運命が待っているだけだ(焼菓子なので法的に問題ないと思われる)。 用もないのに頻繁に出入りしていた少年は、製造過程を勝手に見学しながら、そのB級炭酸せんべいを勝手にパリパリ食べたりしていた。製菓隣組の利点を活かした特権行為といえる。 少年はそれに目をつけた。普段なら接する機会のない規格外品を持っていけば、みんな珍しがってくれるのではないだろうか。うけるのではないだろうか。 思い立った彼は、炭酸せんべい工場に向かった。 従業員たちはいつもと変わらず、「ああ、あそこの工場のバカ息子が遊びにきた」という温かい眼差しで迎え入れてくれる。 少年は工場長のおじさんを見つけて声をかけた。 「失敗したせんべいちょうだい。遠足のおやつに持ってくねん」 「かまへんで。どれくらい持ってく?」 「200円」 量のつもりで尋ねたのだろうが金額で返され、おじさんは唸った。物が物だけに値段設定などされていないからだ。 「200円分か……」 * * * スーパーでお買い物しましょう。お野菜、お肉、お魚、牛乳、卵を買いましょう。冷凍食品4割引きだわ買いましょう。お惣菜のコーナーを覗くのも忘れずに。明日の分のパンも買っておきましょう。 お会計しましょう。カゴいっぱい買っちゃった。でも一番大きな袋なら、なんとか1つに入りきるかな? * * * という場合に、スーパーのレジなどでもらえる最大サイズのポリ袋を頭に思い浮かべてほしい。 それに炭酸せんべいが満タンに詰め込まれているのを想像してほしい。 それが2袋。 袋を2つ渡され「好きなだけ入れていき」と言われれば、詰め込めるだけ詰め込む。加減なんて知らない。それが子供だ。 さすがに1つは置いていけと家族に止められ、彼は遠足に出かけた。 伝説の始まりである。 背中のリュックより、手にしたスズメバチの巣を思わせる塊の方が重さも体積も上回っているのだ。つかみのインパクト十分である。 「なんやそれー」 「おやつ。炭酸せんべい100円分や」 渦巻く大爆笑。 道中も「ちょっと見してくれ。持たしてくれ」と話題の中心に炭酸せんべいがあった。クラス全員の宝物といった扱いだ。 そしておやつの時間。もちろん一人では食べ切れないので振るまいまくり。見たことのないバラエティに富んだ炭酸せんべいにみんな大満足である。ちりめんじゃこも豆も今回は(何を仕込んできたか憶えていないが)負けを認めたに違いない。 教師も彼の実家が菓子製造業なのは知っているので、この暴挙がぎりぎりでグレーと判断したのだろう。冷笑を浮かべつつ、少年にもらった歪んだせんべいを食べていた。 少年は英雄になった。 ここで英雄譚は幕を閉じる。何の前ぶれもなく、次の遠足からはおやつが学校側からの配給制に変わってしまったからだ。 彼らは落胆した。発表の場を一つ失ったことを心から悲しんだ。 おやつのシステムが変更になったのは、見えないところで何か汚い大人の力が働いたからに違いないと、自分たちの非力さを呪った。 数十年経ち、冷静になって思う。 見えないところで汚い大人の力が働いたには違いないが、システムが変更になった根本的な原因は明らかに少年にある、と。 彼もまた、大人をいじる限界点を見誤っていたのだ。 大人の立場になってわかることがある。 PR |
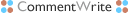 |
|
|

|
|
トラックバックURL
|
|
忍者ブログ [PR] |






 CATEGORY [
CATEGORY [ 