|
2025/07/08 22:45
|
|
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
|
2008/10/24 17:34
|
|
ぼちぼち紅葉の便りも聞こえ始めるこの季節。 皆様はいかがお過ごしだろうか? 住宅の設計を生業とする私にとって、この時期は一年の中で最も忙しい季節と言える。 家を建てようというお客様の多くは、年度内(来年3月まで)に新居への引越しを済ませたいと考える。 木造住宅の場合、着工から完成・引渡しまで大体4~5ヶ月。 逆算すると、ちょうど今頃がその着工の時期に当るのである。 着工の直前には、建築確認申請はじめ各種申請、意匠図面の最終修正、施工図面(構造図等)の作成、そして地鎮祭・・・などなど、やらなければならない事が目白押しなのだ。 ちなみに私は先月2件、そして明日もう1件、地鎮祭の予定が入ってたりする。 そんなわけで、またまた投稿が遅れてしまい申し訳ありません。 で、今回はその「地鎮祭」についての話。 「地鎮祭」とは、建物を建てる前に、その土地を清め、お祓いをする事で、建物が無事完成する事と、工事の安全と、これからその建物に住まう人達の繁栄を祈願する宗教的儀式。神式では「とこしずめのまつり(又は、とこしずめのみまつり)」と呼んだりする。 読者の皆さんの中でも、すでに住宅を取得されている方もおありと思うが、分譲住宅やマンションの場合、その地鎮祭に参加する事は殆ど稀であろう。 おそらく「聞いた事はあるけど、実際に参加したことは無い」という人が多いのではないかと思う。 建築業者でない限り、参加したことがある方でも、せいぜい1~2回ではないだろうか。 建物を建てる際に必ず行なわなければならないという訳ではないので、最近では行なわない人も珍しくない。 私は特に信心深い人間でもなく、特定の宗教に興味を持っているわけではないが、建物ができたあとで、もし何か良くない事が起こった時に、 「やっぱりちゃんと地鎮祭をしなかったからだ」 と、家族や親戚、友人などに言われたり、自分がそう後悔しないために、一応行なっておいた方が良いとは思う。 地鎮祭には、神式・仏式・キリスト教式があり、それぞれやり方は異なるが、日本では神式が殆ど。 私は建築業界に入って20年近く経つが、過去キリスト教式はゼロ、仏式も1回だけ。 そのただ1度の仏式の地鎮祭に参加した時は、とても辛かった思い出がある。 現場は横須賀市のとある海沿いの町。 その日はちょうどダンス部夏合宿(たぶんジメや大五郎たちが一年の年)の最終日。太陽がギラギラと照りつける蒸し暑い真夏日だった。 OBとして合宿に参加していた私は、仕事のことなどすっかり忘れ、前日の打ち上げを心置きなく楽しみ、そのまま他のOB達と夜通し飲み明かしていた。朝になり、まだ二日酔い状態のまま車を運転(道交法でいう酒気帯び状態だったかは微妙ですが、イケませんね。もう時効ですが、二度としません!)、金谷からフェリーで久里浜へ。そこから10分ほどで現場に到着。まだ下を向くと気持ち悪い状態。 ほぼ同時にお施主様・お坊さん・他の社員(当時私は住宅会社に勤務、担当者の一人として参加)も到着。 式に先立ち、3尺(約90cm)ほどの棒(おそらく魔除けの意味であろう言葉が仏教文字で書かれている)を建物予定位置の中心部に埋めることになった。 まだアルコールが抜け切れず、下を向くだけで気持ち悪いのに、炎天下の中、1m近い穴をスコップで掘るという作業は過酷を極めた。 ようやく埋め終わり、式が始まる。 始まってしまえば、特に私のすることは無く、あとはお坊さんにお任せで、ただお経を聞きながら殆ど立っているだけ。 だが、これがまた辛い。。。 炎天下の中だというのに、スーツは着てなきゃなんないし、暑いし眠いし気持ち悪いし、そして長い! 神式であれば、30~40分程度なのだが、この日は仏式、宗派にもよるのだろうが、一時間以上はかかっていた。 何度倒れそうになったことか。 その日の午後は仕事にならなかったのは言うまでもない。 さて、特にオチも無い昔話はこの辺にして、一般的な地鎮祭(神式)についての話に。 と言っても、地鎮祭に参加するに当っての特別な知識は必要ないが、一応自分が施主である場合に知っておいた方が良い事を何点か。 まず大切なのは “気持ち”。 その土地に宿る神様を敬い、無事良い家が建つ事、家族が幸せになる事、をお祈りする気持ち。 その気持ちさえしっかり持っていれば、少々作法を間違えても気にすることはない。 次にどこの神社さんにお願いするか。 地元に親しい神社さんがあれば、それに越したことはないが、そうでなければ、住宅会社や工務店さんにお任せするのが良い。 神社さんによって地鎮祭の様式も微妙に異なるし、竹やお供え物など、色々準備するものがあるので、勝手知ったる者同士の方がスムーズだからだ。 大手の住宅会社などがよく依頼している神社さんだと、地鎮祭を非常に多く行なっているため、とても地鎮祭慣れしている。 というとあまり聞こえは良くないが、そのメリットもある。 殆どの施主にとっては初めての地鎮祭。色々不安もある。その辺をよく理解しているため、式の始め若しくは式中に、その様式や作法についてなど丁寧に説明してくれたりするし、お供え物なども全て神社側で用意してくれたりする。費用も大体決まっている。やや裏話になるが、金額によってお供え物のグレードを使い分けたりしてるところもあるらしい。例えば7万円コースだと鯛の尾頭付きの大きいのが付くとか、お供え品が豪華10点盛になるとか。。。あくまで例えばで、そんな話を聞いた事があるって程度。 まぁ、大切なのは気持ちなので・・・ 逆にあまり慣れていない神社さんだと、竹や砂、お供え物(海の幸&山の幸各数点と酒、米、塩など)などを全て施主側で用意しなければならなかったりする。 なかにはやたら不機嫌な神官さんもいたりして、お祝い事なのになんだかこっちまでブルーになったりしたことも。 式の流れについては、各神社さんによって微妙な違いはあるが、大まかな流れとしては、お祓い・お清め~降神~祝詞奏上~鎌入れ・鍬入れ・鋤き入れ~玉串奉奠~昇神~直会、といった順序で行なわれる。 そのほとんどは神官さんが執り行い、参加者はただ立っているだけっていう感じ。 参加者が行なうのは、鎌入れ・鍬入れ・鋤き入れ~玉串奉奠ぐらいで、あとは直会の時にお神酒で乾杯するのと、お祓いの際に頭を下げる事ぐらい。 鎌入れ(くさかりぞめの儀とも言う)というのは、設計者が木製の鎌で「エイッ、エイッ、エイッ!」と言いながら、祭壇脇の砂山に植えられた草を3回刈る儀式。 鍬(くわ)入れというのは、施主が木製の鍬で「エイッ、エイッ、エイッ!」と言いながら、その砂山を3回崩す儀式。 鋤(すき)き入れれというのは、施工者が木製の鋤で「エイッ、エイッ、エイッ!」と言いながら、その砂山に3回鋤を入れる儀式。 私が参加した場合は、大抵この鎌入れの儀を行なわせてもらうのだが、お祝い事であるし、3者の行なう儀式の最初になるので、次の施主さんの緊張をほぐすためにも、なるべく威勢良く大きな声で(宇野君っぽく)「エイッ!」と叫ぶようにしている。隣近所に聞こえるくらい。でもこれがお客さんにはなかなか好評。 不慣れなお施主さんは、緊張や照れもあるのか、どうしても小さな「エイッ」になってしまう。やっぱりお祝い事なのだから、ここは景気良く発声してほしいものだ。 玉串奉奠というのは、玉串を神様にお供えして、お祈りをする儀式。 参加者全員が一人ずつ、神官から渡された御榊(玉串)を手元で「の」の字を描くように回して祭壇にお供えし、2礼2拍手1礼をする。 私が参加した場合は、この時の拍手で、いかに小気味良い大きな音をたてられるかに神経を注ぐようにしている。 うまく手の平に空気を含めるようにして、手首のスナップを利かせると、小気味良い「ポンッ!」という音が出るのだ。 ただしここで両肘を広げすぎると、私のような太り気味の人間がやると土俵入りのように見えてしまい、参加者の失笑をかうので注意が必要だ。 不慣れなお施主さんなどは、緊張もあるのか、どうしても「ペチッ」というちょっとしみったれた感じの音になってしまう。 神官さんはさすがに慣れていて、とても小気味良い「ポンッ!」という音を出すのだ。この音でその神官さんの熟練度がわかったりする。 たまにちょっと湿った音が出たりする神官さんだと、「あぁ、まだこの人は新米さんなのかな」などと思ったりしてしまう。 いけませんな、神聖な儀式の最中にそんな事を思ったりしては・・・いつかバチが当たりそうだ。。。 バチ当りついでに、もう一つ神官さんの熟練度をはかる項目として、 はじめの方にある降神の儀と、終わりの方にある昇神の儀というのがある。 これは神様が天から降りてくる時と天に帰る時の儀式で、神官さんが 「…ォォォオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオォォォ…」 と、始めはかすかな声で、だんだん大きくなっていき、まただんだん小さく「オ~」と発声する。 この「オ~」の声が、より大きく、より小さく、より滑らかに、より長く発声できる神官さんほど、熟練度が高いと思われる。 あくまで私の憶測でしかありませんが。。。 さて気になるその費用だが、前述の「慣れてる神社さん」の場合、神社さんにお納めするのはお供え品込みで3~5万円ぐらい。 「初穂料」(「玉串料」でも良い)と書いた熨斗袋に入れて、直会の直後に神官さんに渡す。 他の参加者へのご祝儀等は原則必要無いが、出しても可。 出す人・出さない人は大体6:4くらいかな。 住宅会社によっては受け取らない会社もあるが、出す場合、代表でだれか一人にあげるのでもOK。 住宅会社ではなく大工さん(又は地元の小さな工務店)に工事をお願いしている場合は、お酒を持ってきてくれたりするので、足代として出してあげた方がベター。その場合の額の目安としては5000~10000円くらいかな。 神社以外の人へのご祝儀は、これもまたあくまで“気持ち”の問題なので、来てくれた事への感謝の気持ちがあれば、別に出さなくてもいいし、出す場合もその金額にこだわる必要は全くない。 ちなみに、大工さんや住宅会社、または親戚などが地鎮祭に参加する場合に、お祝いのお酒を持ってきたりするが、その際は一升瓶に「奉献」と書いた熨斗紙を巻いてくるのが一般的。たまに「祝地鎮祭」と書いてあるのを見かけるが、これはダメという訳ではないが、あまり好ましくない。 これだとお施主さんへのお祝いとしてもってきた事になってしまう。 地鎮祭に参加する際に持参するのであれば、そのお酒は、まず神様に献上し、そのお下がりをお施主さんがいただく、という形とする方が、地鎮祭の主旨にふさわしいからである。 なので、まずは神様に差し上げるために持ってきました、という意味を込めるために「奉献」と書くことが望ましい。 これは酒屋さんでも知らない人が多く、私が地鎮祭に参加するときもなるべくお酒を持っていこうとしているのだが、酒屋さんに書いてもらおうとお願いしても、なかなか書いてくれないことが多い。「奉献」の字を説明しても、「いや~よくわからないんで」とか、別の紙に書いて見せても、「書いた事ないんで、間違うといけないから」などと言って書いてくれないので、結局自分で書くことが殆ど。これがまた上手く書けないのだ・・・ 長くなってしまったが、まあ何にしても、地鎮祭に関連する全てにおいて、大切なのは“気持ち”なのだ。 ご祝儀を出さなくても、地鎮祭を行なわなくても、「奉献」の字が汚くても・・・・ 怪我の無いよう工事をしてもらいたい、良い家になってほしい、そう思うことが一番大切なのだ。 古くは奈良時代から行なわれていたとも言われているこの地鎮祭。 無形文化財にも近いようなこの慣習は、是非今後とも後世に伝え残していきたい、と個人的には思っているけどねっ。。。 PR |
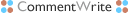 |
|
|

|
|
トラックバックURL
|
|
忍者ブログ [PR] |






 CATEGORY [
CATEGORY [ 