|
2025/11/24 00:03
|
|
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
|
2008/08/26 23:59
|
|
あぁ、8月はついにアナを開けてしまった。山のアナアナ。 なみださしぐむ思いである。 **** さて、周知のように先日オリンピックが終わった。トップアスリートたちの素晴らしい競技に強く心を動かされた方も多いであろう。私も感動することしきりであった。 常ならぬパフォーマンスを発揮する彼ら彼女らの戦いを見て、それがいかに常とは違ったものであったかということを人に伝えるために、報道関係者はもちろんのこと、職場や学校や家庭においての我々も、さまざまな形容のことばを冠して話したり書いたりしたはずである。“驚異的”“圧巻”“豪快”“ダントツ”等々、いくつも挙げられるであろう。 無数にあるそれらの表現を最大公約数的にひとことで言えば、“凄い”である。「超スゲー!」である。 食欲・性欲・睡眠欲を別として、私たち人間が抱きうる諸欲の中で最大のものは「人に自分の気持ちを伝える」ことである。伝えたくて伝えたくてしようがないため、「スゲェ」のことばは頻りに使われ、多様化し、鮮烈さをそこなうことのないように常に変容し続けている。鮮烈なことばをもって、ハナシに生彩を与えたいのである。 ここで言う「鮮烈だ、という感性」は世代によって異なる。変容の渦中に霧散してすでに鮮烈さを失った10年ほど前の「チョベリなんちゃら」は、10年ほど前に春の盛りに突入した世代によって作られ、使われた。そのため、どのような構成・経緯によってチョベリなのか?については推し量ることができても、『なぜチョベリなのか?』に答える資質は私にはない。その世代ではないからだ。湘南爆走族が流行っていたそんな私たちの時代(と地域)には、“全開”“限界”“速攻(?)”などを以って、「スゲー」にあてていた。 「昨日食ったカレー全開辛くてさァ」「あいつ先生に限界喰ってかかってよォ」 勢いだけは、伝わるだろうか? 前置きは以上である。今回も小ネタで勘弁頂くが、“スゲェ”にまつわるぐんまのことばについて書く。 ぐんまのことばは「だんべぇ弁」として明確な特徴を持つが、抑揚・イントネーションは東京のことばとさほど変わらない。であるから標準語に近い、とまで言うつもりはさらさらないが、地域的偏在性の強いことば(俚言)はあまり多く残ってはいない。 そんな中、際立ってぐんまオンリーなことばがある。“スゲェ”“かなり”をあらわす「なから」である。私はこのハナシが好きなため、あるいはこれについて私が話しているのを聞いたことがある方も居られるかも知れない。 ※用例 「昨日喰ったカレー、超辛くてさァ」→「昨日喰ったカレー、なっから辛くてさァ」 「あいつ株で相当かせいだみたいだよ」→「あいつ株でなからかせいだらしいがな」 「光に変えたんだけどスゲー早いんだよね」→「光に変えたんだけどなっから早ェんさね」 右の例によってもおぼろに伝わるかもしれないが、精確に言うとこの“なから”は絶対的な“スゲェ”を直接あらわすのではなく、相対的強意としてスゲェや早ェを修飾する。つまり“かなり”“相当”といったほうがより近い。ウットウしい言い方をすれば形容動詞・副詞である。 同じ人間の本念として、人に伝えたくて伝えたくてしょうがない我々グンマ人は(もしかすると他地域に比べると我々はより強欲かもしれない)ハナシをより鮮烈にしたいとき、この“なから”をココ一番とばかりに投入する。古今東西釣ったサカナはもぅなっからデカいものなのである。 ※ディープな例 「暑いねぇ」「ホントこれは異常だね」 →「暑ィやのォ」「まァずこらァなからだいの」 「なんだ君ハイオクなの?すごいお金かかるでしょう?」 →「あンだおめぇハイオクなんきゃァ?なっから金かかるんべに」 ・・・まったくなからガソリン高いのでなから経費がかさんで困る。 “なから”の紹介は以上である。これでもう突然グンマ人と接せざるをえない状況(←どんな状況だよ)に陥ったとしても君は大丈夫だ! **** 以下は独り言である。 「チョベリ」を分解すれば「超+very」であることは明白である。また、「全開辛ェ」の「全開」は気化器の混合弁をいっぱいに開き、アクセルをふかすことからその勢の凄さをあらわす。常に変わり続ける運命にある“スゲェ”であるが、これらについて我々は「どういった経緯で成り立ったことばであるか」が(まだ)判っている。 しかしながら30年以上の永きにわたって付合っているこの“なから”については、語源は何か?どう派生したものなのか?、よくわからないのである。グンマは意外なほどに郷土愛(プチナショナリズムと言ってもいい)の強い人々が多く、他地域から見れば一種気味悪くすら思われることだろうが、上州弁を収集した書籍が出版され、それが県内書店のベストセラーになってたりする。ったくキメぇよなぁ、ホントに。私も全巻持っているが(←持ってんのかよ)かなり精緻に編まれたその本においても、“なから”の語源については推測の域を出ていない。 「なかなか」がナマった、“半分くらいまで”という程度量を表わす「半ら」ということばが次第に「半ば以上」を含むようになった、などさまざまである。それぞれ一定の整合性があり、多分、その全てが正解なのだろうとおもう。 だが冒頭から述べ続けてたように、ことばは常に常に変わり続けるものなのであるから、語源を突き詰めるなど、よほど困難と言わねばならない。もっと言えば、ナンセンスなことなのかも知れない。自分の千年前の先祖がだれであったかを(知ってはみたいが)、知ってどうするのか。 さりながらことさらにこだわるのは、北海道において“スゲェ”とか“ひどく”を「なまら」と言う、ということを知ったためである。特徴的な語感をもつこれらがグンマと北海道にあることは、偶然なのだろうか? 参考までに調べてみると、“なまら”についても語源はまちまちであるらしい。一説に「生のタラ(鱈)」が“なまら”に転訛したとある。一般庶民にとってタラを含め生の魚は高価で、食膳にのぼることは希であり、“生のタラ”なんて凄い!、が「なまら」になったという。本当だろうか?在来漁撈に携わる人々が多く居たのではないか?もっとも開拓入植後の人々における事情であったならばありうるかと思う。だが何故「タラ」に特化されているのだろうか?もちろん私の無知が猜疑心に変わっているだけのことなのだが、生タラとはにわかにうべなわざるものがある。 ラジオやTV以前、ことばは時代時代において首都から波紋のように拡がって行き、波が障害物にあたって変化するように地勢地政の狭間にとどまり、定着し、そしてまた変化をしてきた。ここグンマでは語尾につける「〜ね」がときより「〜の」に変化し、同意を求める時には語意を強め、さらに強まると「の!」だけで成立する(※「そうだよね!」を「の!」と言うだけで済ませる)のだが、以前山口出身のよすこと話していて、かの地にもまた「の!」があることを聞き、おもしろく思った。もっともこういった例は無数にあるのだろうが。 果たしてグンマと北海道につながりはあるか? ・・・ゼンゼンないかも知れないが、あると仮定してあれこれ推理することも、つまらないことではない。 以上独り言である。 無論そんなことより先に考えねばならぬさまざまな課題が私の目の前に山積しているため、私の脳内妄想ゲームはたまにしか開催されない。なからなまらの問題解決は尚闇の中である。 **** あぁ、ライトに書くつもりがなっから長くなっちまった。 ならね〜。 PR |
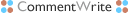 |
|
|

|
|
トラックバックURL
|
|
忍者ブログ [PR] |






 CATEGORY [
CATEGORY [ 