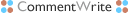佐久間貴志(さくまたかし)
東京大学理学部名誉教授、日本数理解析研究財団顧問、数学者。今日の数学界に多大な影響を与えた人物である。
1921年(大正十年)生まれ。埼玉県東日吉村(現日吉市)出身。
貧しい農家だった実家に負担をかけぬようにと、中学時代、埼玉造士会の特待生試験に応募。県全体で五名の狭き門を抜け合格。
当時の制度により、特待生は必ず士官学校を受験するよう義務付けられていた。気乗りはしなかったが、授業料免除のみならず給料が支給されることもあり(大卒月給が40円の時代に基本年俸1900円)、貴志は陸軍士官学校を受験し合格。市ヶ谷の陸軍士官学校予科に入校する。
1939年(昭和十四年)、士官候補生として座間の本科へ入校する頃には、授業の大部分が軍事関係となっていた。その中の一つ「測図演習」が貴志の後の人生を大きく変えることになる。
方位磁針とわずかの製図用具のみで、与えられた地形を地図化していくこの授業で、貴志は頭抜けた好成績を修めた。通常三人、少なくとも二人一組で行うこの演習において、彼はたった一人で教師陣よりも早く正確に地図を描くことができた。当時のことを後に貴志は
「等高線の声が聞こえていた」
と表現している。
翌年、日本軍は真珠湾を奇襲。太平洋戦争へと突入する。
戦況が悪化するなか、貴志は将校の養成機関である陸軍大学校に進学。同時に陸軍中尉歩兵中隊長の肩書きを得る。教授部教官にも命じられ、本科における数学・物理及び測図演習を教える立場となる。
しかし大学校卒業年次の1945年(昭和二十年)、一度も戦場に立つことなく終戦。公職追放となった彼はすべてを失う。
戦火を免れた実家に戻り、細々と家業を手伝っていたところ、士官学校卒業生には大学受験の資格が与えられることを知る。給金に手を付けずにいてくれた家族の後押しもあり、貴志は東京工業大学理学部数学科に入学。一時教職を志すも、自身の吸収意欲は衰えを見せず、東京帝國大學(現東京大学)大學院に進学。理学研究科で修士号取得。
国内での研究に限界を感じた貴志は、迷わず渡米。コロンビア大学で博士号取得。研究対象は「ブルバキ数学原論における非特異射影多様体と代替積分」(翌年妻となるプラウダ・シェルジンスキーと共同研究)。代数曲面に革命的ともいえる幾何的解析手法を持ち込んだこの研究は、学会を大きく震撼させた。その根底に士官学校時代の測図演習があることは言うまでもない。同研究にてエスタンブロー賞を受賞。
コロンビア大学講師、ハーバード大学助教授、マサチューセッツ工科大学准教授・教授を歴任。同大学在任中、「双有理複次元因子および局所線束解析の標数同値演算理論」で日本人として初めてカニュラール賞を受賞。三次曲面を感覚的に捉える手法(著書「踊る座標」に詳しい)が一過性のものでないことを知らしめ、世界で五指に入る数学者としての地位を揺るぎないものとする。
欧米の複数の大学・研究機関から終身身分保障付きで招聘されるものの、それらの話をすべて丁重に辞退し、「やるべきことがある」と帰国。
ひとまず東京大学教授の地位に落ち着き、教鞭をとりながら、現在「佐久間係数」「佐久間次元」としてお馴染みの各種論文を発表。また、妻のプラウダとともに「ゼロ」や「無限大」の新解釈など哲学的といえる分野にも傾倒し、ユニークな著書を多数発表する。
しかし貴志は机上論理ではなく、あくまでも「数学の最前線」にこだわっていた。職業軍人として戦争の現場に立てなかった悔しさ、そして戦争により同期の仲間を多く失った無念が影響していると、後に彼は語っている。
1981年(昭和五十六年)、名誉教授になったのを機に、理系科目の新しい教育を研究模索する「日本数理解析研究財団」を設立。理系離れが叫ばれる昨今、小・中・高校の特別授業に講師として積極的に赴き、数学の面白さ、楽しさを子供たちに説いて回った。後に貴志の弟子となる大越秀一(1998年にカニュラール賞を受賞)も、中学時代に彼と出会い、それをきっかけに数学者になることを決意したというのは有名な話である。
21世紀に入ってからは体調を崩すことが多くなり、回数こそ減ったものの、彼は体が許す限り地域の学校や講演会など、自身にとっての最前線へと意欲的に出向いた。
自宅療養となってからも教科書や参考書、問題集の制作に取組み、教育現場に対する情熱は冷めることがなかった。
そして2006年(平成十八年)、貴志は八十五年の生涯に幕をおろした。妻プラウダに看取られての穏やかな最期だった。
以下に彼の最後の仕事となった、晶研社発行「さんすうチャレンジ」の一部を示す
(*資料1)。貴志自らが問題文に登場することにより、親しみやすく、子供たちに対する愛情溢れる内容となっている。
・資料1
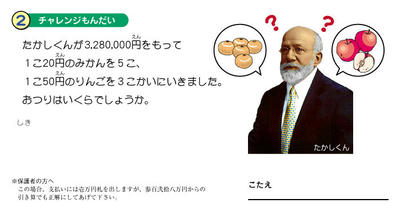
参考までにプラウダも同書においてコラムのコーナーの執筆を担当しているが
(*資料2)、残念ながら「小学生向けにしてはいろいろな意味で難解である」と、あまり評判はよくなかった。
・資料2
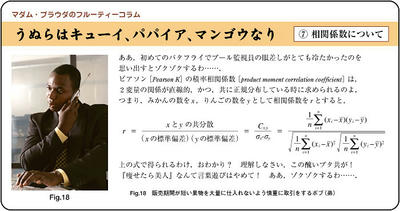
※ 今回の話はそれこそ全編にわたってフィクションにもほどがあります。
PR